
弁護士コラム
第187回
『【退職代行 弁護士が解説】退職時に入社祝金は返す必要があるの??』について
公開日:2025年11月5日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第187回は『【退職代行 弁護士が解説】退職時に入社祝金は返す必要があるの??』についてコラムにします。
2025.10.28「日経ビジネス」「モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ」で弁護士清水隆久が取材を受けて解説しています。
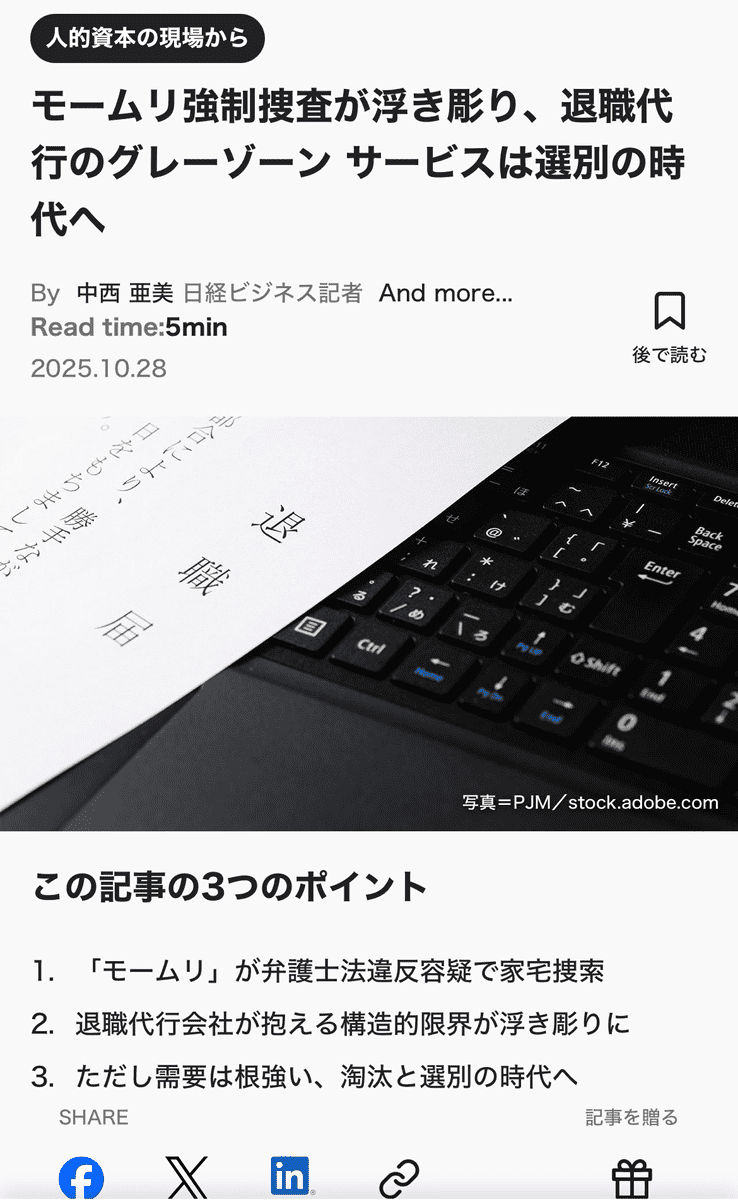
入社時に祝金を受けるケースで、退職時に返還請求を会社から受けるケースが増えています。そこで、今回、どのようなケースで返還が必要であるか解説します。今回のコラムも弁護士の清水隆久が解説します。
入社祝い金の返済(返還)についてお悩みでしたら、弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行からお申込みください。

目次
1.❶ 返還するケース
入社祝金を『貸付』とし、退職時にその返還を会社が請求するケース
→
入社祝金を民法第587条『金銭消費貸借契約』で支給する場合には、退職時に『返還請求』することは、労基法第16条『賠償予定の禁止』にあたりません。
→
したがって、会社から入社祝金を請求された場合には支払いする必要が法律的にはあります。
次に、請求された場合でも、給料と相殺することは、労基法第17条で禁止されています。
→
会社の処理上、入社祝金返還について請求されても給料の支払いを受けられますので、未払いになったケースでは、労働基準監督署に『申告』するケースが増えています。
参考裁判例
東京エムケイ事件(東京地裁 H26.1.20)
2.❷ 返還不要なケース
入社祝金を入社時に支給し、入社から2年以内に退職したケースで、会社から入社祝金の返金請求を受けたケース
→
償還期間などを設けていない誓約書などを書いているケースでは、労基法第16条『賠償予定』の禁止にあたり会社は退職者に対して入社祝金の返還請求ができません。最近では当たり前のルールになりつつありますが、❶とは区別するようにしてください。
参考裁判例
日本ポラロイド事件(東京地裁 H15.3.31)
3.❸ ❶❷以外のケース
入社祝金が『貸付金』『立替金』『ローン』などの記載があっても、実態は、雇用におけるインセンティブにあたるケース
→
実態を判断して、雇用におけるインセンティブにあたる説明方法、運用目的、契約内容が合理的なものでない場合には、労基法第16条に違反して無効となります。
→
『貸付金』『立替金』『ローン』などの契約書を結んでいたとしても、①契約時にどのような説明をしていたのか、労務報酬性があるか、償還期間、一括返済を求めることで過重な制約を課し自由な退職を事実上制限するか、など諸般の事情を考慮して、労基法第16条ないし第16条の趣旨、労基法第5条などから無効と判断される場合もあります。
参考裁判例
⑴ BGCショウケンカイシャシャリミテッド事件(東京地裁H26.8.14判決)
⑵ グレースウィット事件(東京地裁H29.8.25判決)
4.まとめ
入社祝い金については、退職代行時のご相談が多い一つです。その際、会社側が支給した入社祝い金相当額と最終給与を相殺するケースがあります。相殺については、労基法第24条の賃金全額払いの原則に反します。
仮に、会社が一方的に「相殺」して、給与未払いを強行した場合には、退職者は、労基法第23条により「請求」を行い、7日以内に支払いしてこない場合には、所轄の労働基準監督署に申告することで是正を行う場合もあります。入社祝い金についてお悩みでしたら私までご相談ください。
給与未払いに対する「申告」方法については、コラム第71回をご参照ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。