
弁護士コラム
第104回
『教職員の休職代行(病気休暇代行)』について
公開日:2025年4月11日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第104回は『教職員の休職代行(病気休暇代行)』についてコラムにします。
公立小中高の教職員の方からの休職代行の依頼は多いです。自衛官に次いで2番目の多さになります。
ここ最近、私が盛んに休職代行のコラムを書いていることや、広告をしていることで、全体として、公務員の方の休職代行(休職手続きの代理代行)は増えていますが、その中でも学校の先生の休職の割合が多くなるのは、他の公務員の方に比べてストレスが多いのも理由だと私は考えています。
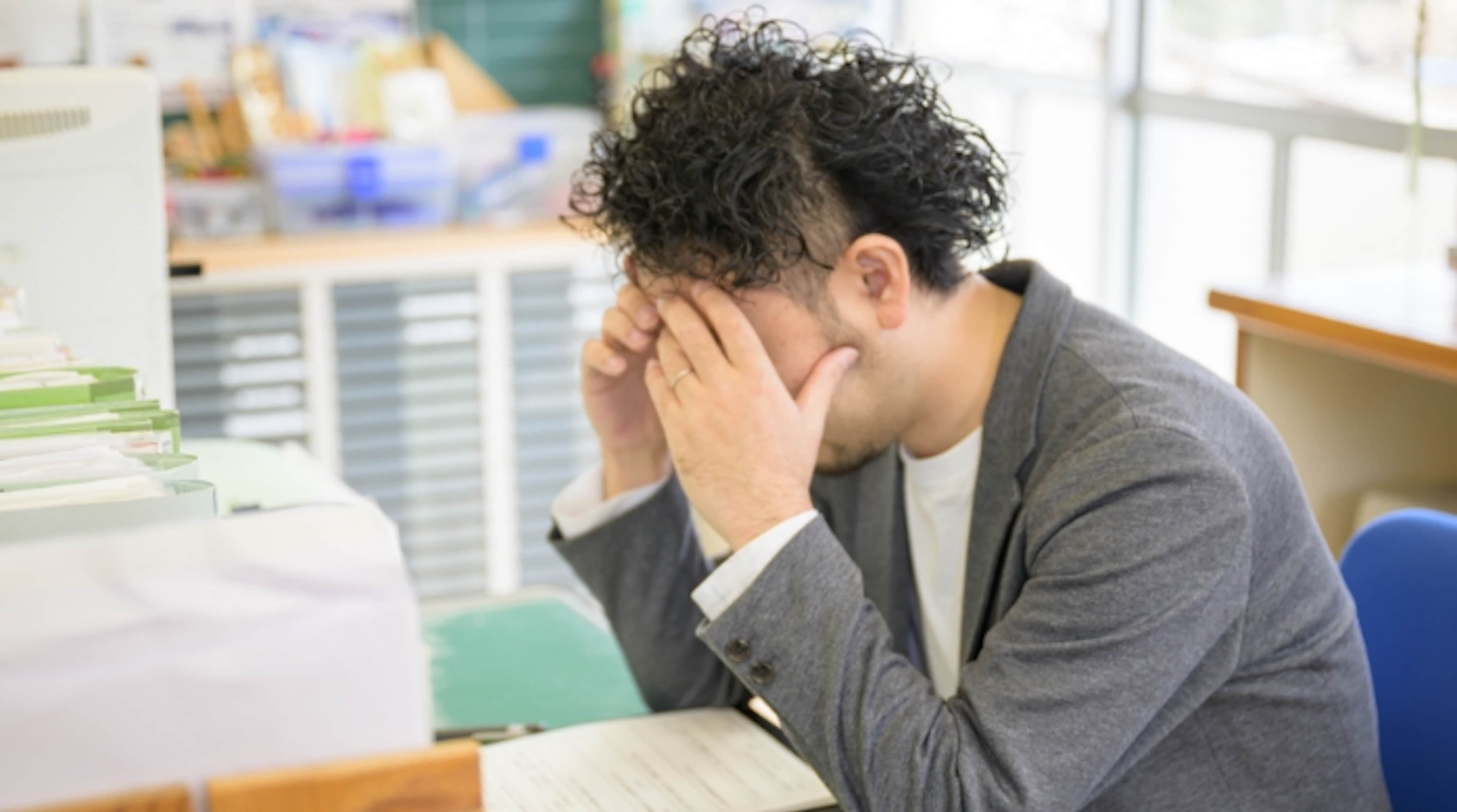
目次
1.教職員の休職代行(病気休暇代行)について
学校の先生の採用区分としては、①正規職員と②臨時的任用職員等に分かれています。
その際、①②の採用区分に応じて、病気休暇から休職の給与の保障が異なります。
まず、①正規職員については、適応障害、うつ病などの体調不良の診断書が出た場合には、病気休暇(90日)→休職(1年)→傷病手当金申請(1年6月)の流れになります。
( )内は、給与保障の日数になります。なお、休職は、給与の80%保障になります。傷病手当金は、給与の2/3になります。
その一方で、②臨時的任用職員の場合には、病気休暇(90日)→休職(無給)の流れになります。したがって、病気休暇については、90日間は、100%の給与保障はされますが、休職に入った段階では、無給となるため、傷病手当金申請をするようになります。
今までの休職代行の依頼は、①正規職員の先生よりも②臨時的任用職員の先生の方が多いため、病気休暇の代理手続きをした後、休職代行を受けると同時に傷病手当金申請サポートを受けるケースがほとんどです。
傷病手当金申請については、申請書類を職場から取り寄せて、書き方のアドバイスをしたり、職場との間に入り、私の方で申請をスムーズに行うための手続きを取ります。傷病手当金申請についてお困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。
教職員の公務員の方が私の方に病気休暇や休職代行を依頼した場合には、一般的に、職場や教育委員会との電話連絡や面談は不要になります。
例えば、職場でパワハラを受けているケースも多くありますので、精神的に限界であるケースでは、弁護士に休職代行(病気休暇代行)を依頼するメリットは大きいと考えます。精神的に限界でありましたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。
2.まとめ
学校の先生のストレスはかなり大きいと私は考えています。また、休職の申し出をすると退職勧奨を受けるケースも多くあるようです。
実際、私が休職代行の手続きをとるにあたっても、学校長から退職勧奨を受けることが多々あります。理由はいつも同じで、補充人員の関係を主張されます。在籍していると新しい人員を確保できるないようです。
場合によっては、代理人弁護士の揚げ足を取り始めて代理人弁護士が嫌がらせを受けるケースもあります。
その一方で、退職の意向を示した後は、一切の圧力もなくなります。ご自身で休職の手続きをされるのは相当なストレスがあるものと思慮しています。
繰り返しになりますが、教員の方で、体調不良により、しばらく休みたいと考えている方は、遠腹なく私までご相談ください。力になります。
・参考コラム
第3回『退職代行時の傷病手当金請求』
第4回『休職代行』
第24回『弁護士による休職代行』
第46回『公務員のための休職代行』について
第103回『公務員のための傷病手当金申請サポート』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。