
弁護士コラム
第184回
『【弁護士が解説】モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ』について
公開日:2025年10月28日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第184回は『【弁護士が解説】モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ』についてコラムにします。
2025.10.28「日経ビジネス」「モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ」で弁護士清水隆久が取材を受けて解説しています。
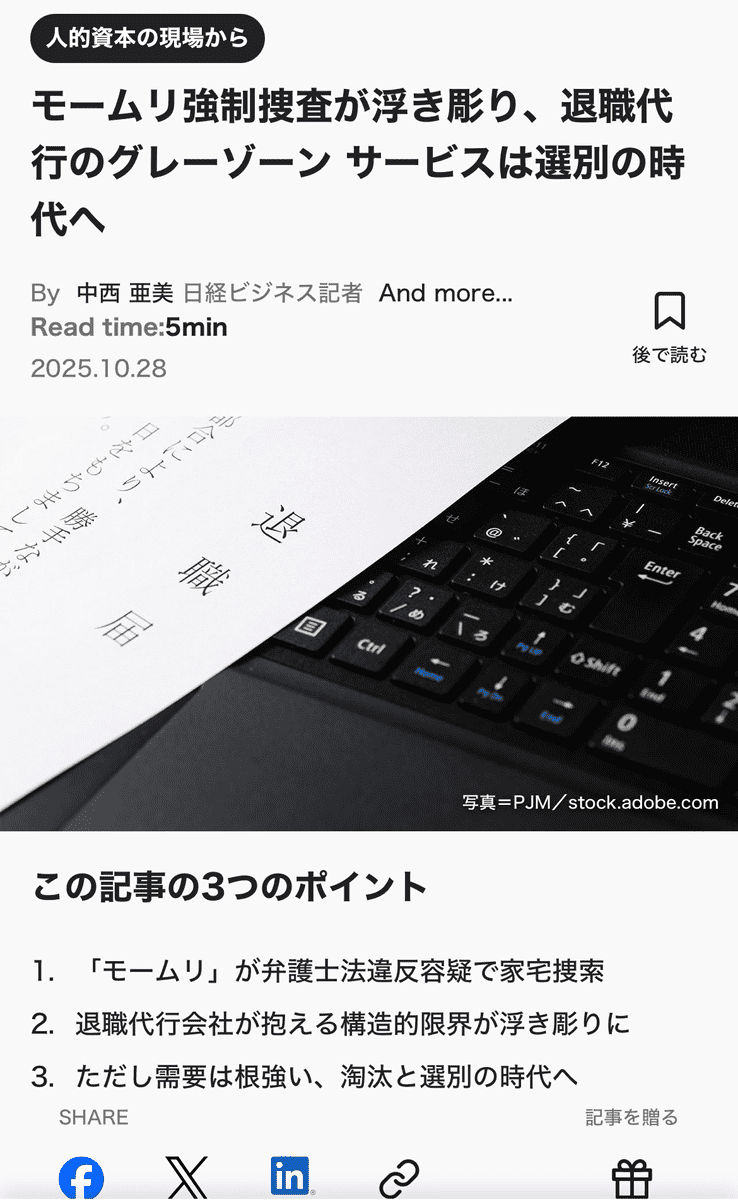
引用記事
【(前略)…一方で、民間の退職代行会社によるサービスには制約もある。具体的には、退職代行会社が担えるのは、あくまで「退職の意思を伝える」役割にとどまる。残業代の支払い交渉や有給休暇の取得調整など、労働条件を巡る法的な交渉(いわゆる法律事務)は、弁護士しか行うことができない。弁護士資格のない者が代理人として交渉に関与すれば、「非弁行為」として弁護士法72条に抵触する。
しかし、「実際には退職代行会社が法的な交渉をしているケースも少なくない」と、弁護士法人川越みずほ法律会計の清水隆久弁護士は指摘する。モームリでも、弁護士への紹介料問題に加え、退職を巡って会社側と法的な交渉を行っていた可能性が浮上している。なお、弁護士への紹介料の授受に関しては、報酬を得る目的で法律事務を弁護士にあっせんする行為が同法72条で、弁護士が業者と提携し紹介料を支払う行為が27条で、それぞれ禁じられている。
…(中略)…
もっとも、法律事務を一切行わないことを明言する退職代行サービスだからといって、利用者が安心できるわけではない。本来であれば取得できる有給休暇などの権利について十分に説明や交渉をせず、結果として損をしてしまうケースもある。「こうした実態は、消費者保護の観点からも問題視されかねない」と清水氏は話す。今回の事案は、退職代行会社が抱える構造的な限界とグレーゾーンの実態を浮き彫りにしたといえるだろう。今回の家宅捜索を機に、こうしたグレーゾーンに対する捜査当局や消費者の目は一段と厳しくなるとみられる。
…(以下略)】
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00636/102700057/

目次
1.退職代行会社の「退職代行」の限界
先日の某退職代行会社が非弁行為の疑いで、警視庁から家宅捜索を受けた事件は皆さんの記憶に新しいと思いますが、その事件を契機に各メディアは、退職代行会社の「退職代行」の限界説を主張しています。退職代行会社の特徴として、①②が考えられます。
①「退職の意思」を伝えるだけしかできません。
②退職には、退職意思を伝達するにとどまらず本来であれば取得できる有給休暇などの権利について十分に説明や交渉ができていません。
①「退職の意思」を伝えるという観点からすれば確かに伝えれば十分な職種があることも否定できません。例えば、派遣会社を退職するにあたって、退職代行をして揉めるケースは少ないため、退職代行会社でも十分なのかもしれません。
しかしながら、「退職の意思」を伝えるだけでは対応できない職種も存在します。また、退職の意思を伝えるだけで、退職日の「指定」はできません。退職日については、会社に主導権があることになります。
仮に、「就業規則上」の規定を根拠に会社が30日経過後を退職日として指定した場合には、退職代行会社は、その「30日経過後」を退職日とせざるを得ません。次の転職先が決まっていた場合には、問題となります。具体的には、次の就職先で「雇用保険」「社会保険」の取得ができなくなる可能性あります。
次の例としては、退職代行会社が行う意思の伝達を無視した場合には、無断欠勤のリスクが格段に高くなります。無断欠勤が14日を超えた場合には、そのまま懲戒解雇される可能性があります。
さらに、懲戒解雇された場合には、退職金が不支給になる可能性があります。「退職の意思」を伝えるというスキームだけではその限界があります。
②退職代行会社の行う退職代行のパータンとしては、❶電話型、❷チェックシート型の二つが一般的に採用されています。❶電話型は、相手の会社とは電話で退職を完了させています。有給残日数が23日であった場合でも、「即日退職」を会社が主張した場合には、退職代行会社は、その「即日退職」を受け入れるしかありません。
退職代行会社がその「即日退職」を依頼者に対して「報告」し、依頼者自身が納得しない場合には、有給について依頼者自身で交渉をする必要が出てきます。
退職の代行とは、「退職の意思」を伝えるだけ・・・・・その裏側では、依頼者の本来的な権利である有給が放棄され、その有給が取れない可能性があります。そのような状況は、消費者の権利を制限し、義務を過重しており、消費者契約法第10条にあたり無効になる可能性もあります。
次に、❶電話型と異なり、某退職代行会社が採用している❷チェックシート型については自分の要望をチェックシートに記入して相手会社に送る方法を採用しています。要望に伴う項目のうち、未払い残業代についても退職代行会社が依頼者にアドバイスをしています。
未払い残業代請求については、「紛争の蓋然性」があると言えますが、その未払い残業代請求に対するアドバイスは「無償」で行っているので、弁護士法第72条の非弁行為にあたらないというスキームを取っています。
ここで、❷チェックシート型の問題点は、そもそも依頼者の要望をチェックシートで送るだけに終始すれば、それは自分自身で内容証明郵便などを送ればそれで足りるという意見がまさに「的」を得ています。
2.まとめ
退職代行会社『モームリ』の家宅捜索における一部ニュース記事では、未払い残業代の「交渉」をしているケースがあるという報道がされていました。
モームリがそうしていると言っているのではなく、私は、退職代行会社が未払い残業代の請求をしている事案を確認しています。例えば、6か月分の交通費の返還と未払い残業代の相殺の意思を代行しているケースがあげられます。
退職代行会社を通じて、相殺の意思を伝えているケースがあります。未払い残業代請求と6か月分の交通費返還との相殺は、『紛争の蓋然性』があり、その意思を代行で伝えるという使者構成をとっても、「交渉」にあたります(弁護士法第72条違反)。私は、今一度、退職代行会社は業務マニュアルを見直す必要があると考えています。
また、退職代行会社が行う退職代行の際、給与の未払いが発生するケースがありますが、その際、退職代行会社は労働基準監督署への未払い給与の申告手続きを案内するだけで、その未払い給与の請求については、アフターフォローがありません。
最近では、未払い給与請求に対するアフターフォローがない点については、「モームリ」の問題点として指摘され始めています。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。